|
そしてこのゲスト・コーナー。連邦共和国だからこそ成り立つ、個人としての存在感。 バンド内バンドの変幻自在なスタイル。際立つ個があってこその快挙。揺るぎない連帯 感があってこその暴挙。組合わせは無数にある。可能性は無限にある。 オール・オブ・ムーンライダーズ。彼らはその手の内を全て晒すつもりなのだろう。特 別なアニバーサリー、この日だけのスペシャル・イベント。 もう一度言おう。今日という日は彼ら自身が待ちわびていたデェイ&ナイトなのだ。 こんな真似が他の誰にできるんだ? 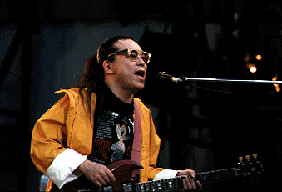 意外な選曲に身震いさせられる。アクゥースティックの響きが乾いた郷愁を焦がす『ト ラベシア』。 意外な選曲に身震いさせられる。アクゥースティックの響きが乾いた郷愁を焦がす『ト ラベシア』。なんて青空が似合う人なんだろう。ストレートな声でぶっきらぼうに唄う良明さん。風 に流されず、切り裂きもせず、ただそこにあるという存在感。いつでもカラッポになれ る潔さと勢いは、ムーンライダーズの中にあってあえて異端と呼ばせて欲しい。ありっ たけの敬意と愛情をこめて。 1988年の僕の部屋は四六時中曇天だった。ラッパを吹いて窓に続く道を教えてくれ たのは"青空のトランペット"。1982年から今までずっと、彼の唄はカンフル剤であ り、トランキライザーでありつづけた。そしてこれからもずっと、見上げればそこに青 空が広がっているに違いない。 ステージを降りるかしぶちさんと博文さん。入れ代わりに武川さんが登場。そしてキー ボードの前には岡田さんが座る。 「途中で指輪がひっかかっちゃって...」 照れ臭そうに弁解する彼の姿に"かわいいっ!"という声が飛び交う。95年に結成され たThreeGraduatesによる『ウエディング・ソング』。かつて、自身の結婚式で聞いた はずの曲だ。20年たった今、自ら唄う岡田氏の胸中はいかほどのものだろう。なんと も心憎い選曲。歌詞は"火の玉ボーイ"のヴァージョン。ダンディズム漂うスウィーティ スト・ダミ声が、まだ陽の落ちない野音に響き渡る。  続いてマイクをとるのは武川さん。この人はヴァイオリンやトランペットと同じく、唄 を歌う時でもクジラ印100%。彼の色気に染められた『ONE WAY TO THE HEAVEN』 が 流れ出すと、僕らは思わず息を飲んで聞き惚れてしまう。実際、客観的な評価をすれば、 歌のうまさでは彼が一番といってもいいんじゃないか?(などと暴言をはいてしまうほ ど、ピッチといい声の伸びといい申し分のない出来だった)。 続いてマイクをとるのは武川さん。この人はヴァイオリンやトランペットと同じく、唄 を歌う時でもクジラ印100%。彼の色気に染められた『ONE WAY TO THE HEAVEN』 が 流れ出すと、僕らは思わず息を飲んで聞き惚れてしまう。実際、客観的な評価をすれば、 歌のうまさでは彼が一番といってもいいんじゃないか?(などと暴言をはいてしまうほ ど、ピッチといい声の伸びといい申し分のない出来だった)。ムーンライダーズをライヴ・バンドだと思っている人がいるとすれば、それはあまりに も的外れな評価だと言わざるをえない。しかし、彼らの本領がレコーディングの場のみ で発揮されるというのも適当な見方とは決して言えないだろう。 彼らにとっては、スタジオもステージも同じく実験の場であり遊び場である。どんなシ チュエイションにおいても、自分達自身がまず楽しむことを条件とするのが鉄則のはず。 多少の例外はあるにせよ、おもしろいと思えないことに対して、彼らがわざわざエネル ギーを注ぐとは考えられない。それほどものわかりのいい大人であったならば、今頃は 大ヒットを飛ばしたのち、ムーンライダーズは円満に散開しているはずだ(笑)。 話しのベクトルが妙な方向に向いてしまったが、とにかく、このリアルタイムで相方向 なライヴにおいては、武川さんの背中がより一層大きく見える。彼がそこにいるだけで、ゆる ぎない安心感が漂ってくるのだ。この人なしではムーンライダーズがありえないこ とを、今更ながらに思い知らされた心地。もう一度だけ言わせて欲しい。 「お帰りなさい、クジラさん」  ゲスト・コーナーのトリを務めるのはこの人。稀代の詩人はあくまで奥ゆかしいそぶり でギターに持ちかえる。そろそろと夜のとばりが降りかけるコンクリート・エリアに、 『駅は今、朝の中』が鳴り響く。日比谷公園の森を抜ける風が木の葉を散らしている。 博文氏の声は蒸気のように熱い。ほとばしる熱気が肌寒さを蹴飛ばしてくれる。 ゲスト・コーナーのトリを務めるのはこの人。稀代の詩人はあくまで奥ゆかしいそぶり でギターに持ちかえる。そろそろと夜のとばりが降りかけるコンクリート・エリアに、 『駅は今、朝の中』が鳴り響く。日比谷公園の森を抜ける風が木の葉を散らしている。 博文氏の声は蒸気のように熱い。ほとばしる熱気が肌寒さを蹴飛ばしてくれる。"アニマル・インデックス"が発表された1985年。僕は夜明けを迎えた後で眠りにつ く日々を送っていた。朝焼けの光の中、カー・ステレオから流れてきたこの曲は、僕の 首に犬歯をつきたてては帰り道を示してくれたのだ。紫色に染まる空を背に、海沿いの 道で聞いた彼の声。置いていけない記憶がここにもある。 ステージの上には再び6人が揃い立った。ムーンライダーズ、バンドとしてのタイム・ トラベルが今また始まろうとしている。 |